異文化理解についての大学入試小論文解答例です。
異文化理解について、ある言葉に持っていたイメージが、大きくかわったあなたの経験について800字以内で述べなさい。
異文化理解について
「異文化コミュニケーション」という言葉に対して、私は日本以外の国々に関する知識がまず必要であるという印象を持っていたが、その印象を大きく覆された出来事があった。
高校1年生のとき、所属していた英語部で浅草でのフィールドワークを実施し、外国人観光客に英語でインタビューを行った。私は相手の国の文化について質問し、彼らは簡潔に答えてくれた。しかし逆に彼らから「なぜ浅草には仲見世が多いのか」や「奈良の東大寺の歴史について教えてほしい」などと尋ねられた際に、どう答えればよいのか全く分からなかった。この苦い経験から、まず私たち日本人が日本文化について理解したうえで外国人と接しなければ、ただ受動的に異文化を取り入れるだけになってしまい、コミュニケーションを図ることはできないのだと痛感した。私はこのフィールドワークを経験して以来、日本にある20の世界文化遺産について調べるなど、日本文化についての知識を積極的に増やしている。
では、海外ではどのように自国の文化を捉えているのだろうか。例えばアメリカでは、エスニックスタディーズという学問が存在する。アメリカには多くの国々からの移民が存在し、文化もそうした人々の価値観を大きく反映している。そのため、アメリカが他国と異文化交流をするためには、国内で少数派とされている有色人種の人々の文化について再認識する必要があると感じた学生たちが運動を起こしたことにより、この学問が生まれた。そして現在、アメリカではエスニックスタディーズが学校教育に組み込まれている。このように、自国の文化についての理解を促す動きは世界でも高まりつつあるのだ。
以上のことから、私は「異文化コミュニケーション」とは、まず自国の文化について十分な知識をもつことで初めて成立するものであると再定義した。そうすることで自国と他国の文化の違いを理解し、真の異文化交流を図ることができると考える。
(798字)
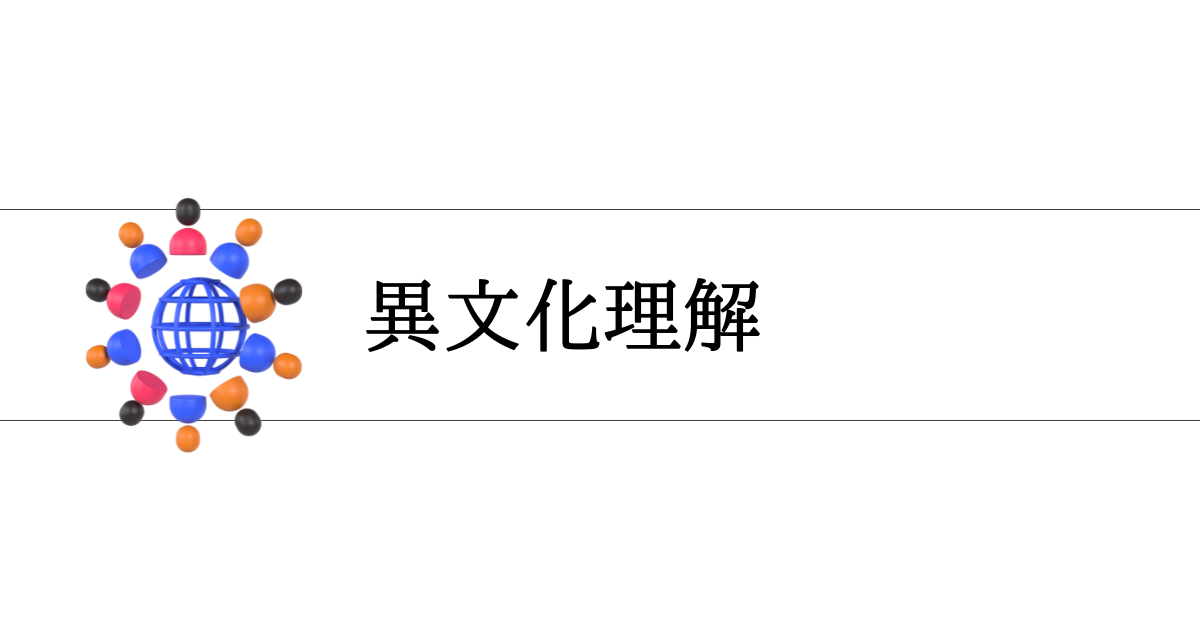
コメント