エシカル消費についての大学入試小論文解答例です。
エシカル消費についての解答例
私は、エシカル消費を根付かせるためには 次の三点のことが重要だと考える。
一つ目は、フェアトレードについての学習の強化だ。日本国内の消費者の大部分は、作物や原材料を生産する人々の労働の実情を知らない。そのため、今後の消費活動を担う若い世代に教育を行うべきである。例として、 フェアトレードを実際に行なっている国や地域への訪問や、該当地域での労働体験などだ。日本は世界でも有数の輸入大国であるので、 海外生産者の労働の質や賃金の向上が期待できるだろう。
二つ目は、企業へのサスティナビリティ商品の展開の推奨だ。国内での商品の割合が増えれば、必然的に購入量も増加すると考えられるからだ。これを実行するためには、政府が作物や原料の購入先のリストアップや補助金の用意をすることが求められる。
三つ目は、国際的な社会課題を消費者に深刻に捉えさせることだ。本文によれば、日本国内で実際にエシカル消費を行って いる人は全体の1割程度であり,ほとんどの 消費者は問題についてそこまで考えていないのではないかと考えられる。そのため、政府は積極的に人権や環境問題などに関するキャンペーンを行い、消費者の利他的な意識の発芽を促すべきである。
以上の3点を行うことで、エシカルな消費 活動が根付くだろう。ただ、商品選択を行う のは消費者自身であるから、自主的に選択を することも大切である。
エシカル消費についての講評
論文の内容は非常に具体的で、エシカル消費の根付かせに向けた戦略が明確に提示されています。フェアトレードに関する教育強化、企業に対するサスティナビリティ商品の推奨、そして国際的な社会課題への消費者の意識向上が、綿密な論拠とともに論じられています。特に、若い世代への教育や企業への政府のサポートがエシカルな消費行動を促進する鍵であると強調されています。消費者の利他的な意識を高めるためのキャンペーンの必要性も理解されており、総合的なアプローチが提案されています。論文は説得力があり、エシカル消費を促進するための具体的な提案が示されている点が評価されます。
エシカル消費についての改善点(抜粋)
<より高みを目指して>
・教育の強化においては、実践的な方法や教育プログラムの具体例が欠如しています。
・企業へのサスティナビリティ商品の展開については、政府の関与に加えて市場メカニズムの活用や企業へのインセンティブにも焦点を当てるとよりバランスが取れるでしょう。
・社会課題に関するキャンペーンにおいては、実行可能性や対象者の心理的影響についての配慮が求められます。
総合的には、提案が具体的でありながらも実現可能性や効果をより深く検討する余地があります。
【一般論】エシカル消費を根付かせる施策
■フェアトレード教育の強化
消費者に作物や原材料の生産者の実情を理解させるために、フェアトレードに関する教育を強化する。
■企業のサスティナビリティ商品の推奨
企業に対して、サスティナビリティ商品の開発・提供を奨励し、これを市場に増やすことを促進する。
■政府の関与と支援
政府は、購入先のリストアップや補助金の提供など、エシカルな商品の導入を支援する政策を検討する。
■消費者への社会課題の啓発
国際的な社会課題に関するキャンペーンを展開し、消費者に対して人権や環境問題などの重要性を啓発する。
■若い世代への教育
未来の消費者である若い世代に対して、エシカルな消費に関する教育を積極的に行い、意識を育む。
■自主的な商品選択の奨励
消費者には自主的にエシカルな商品を選択する意識を醸成し、持続可能な消費行動を奨励する
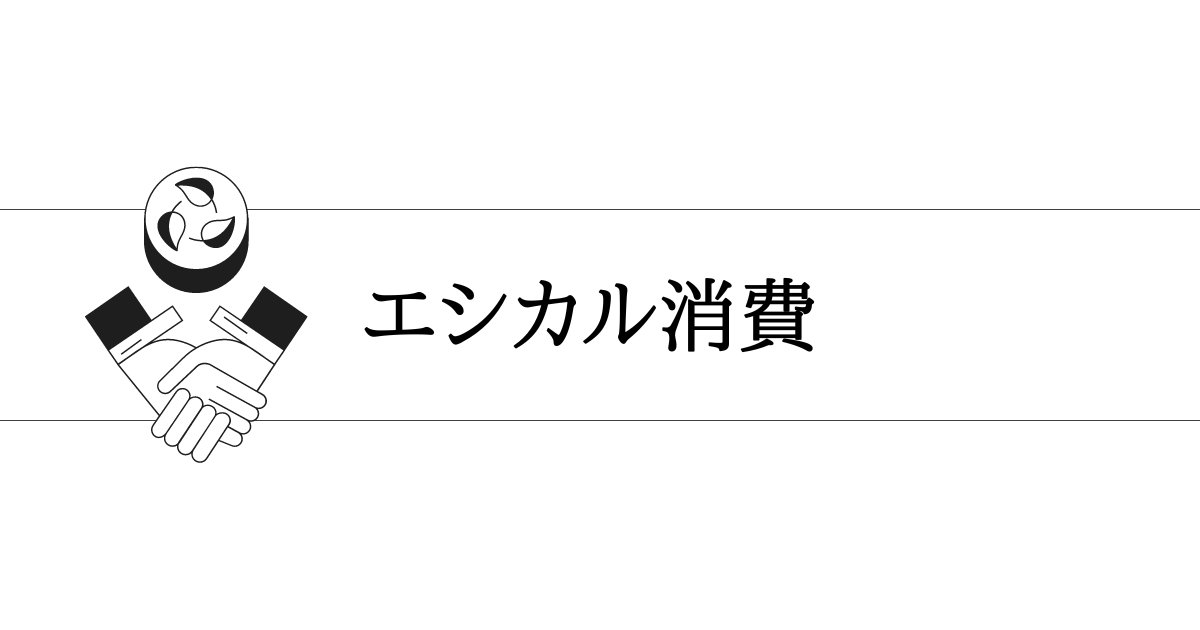
コメント