【2020年度】群馬県立女子大学文学部の大学入試小論文解答例です。
お互いの間に共有できないでいる言葉
筆者が述べている通り、おたがいのあいだに共有できないでいる言葉は存在すると考えられる。インターネットの発達により、人と直接会わなくても自分の思いを伝え合うことが容易になった。たが、そうなったからこそ、言葉にのせた伝えたい思いが上手く相手に伝わらないことが増えたのも確かである。
なぜなら、その言葉が自分の知っている意味だけで使用されるものだと無意識のうちに捉えてしまっているからだ。ある言葉を見た時に真っ先に思い浮かべるのは、自分が捉えているその言葉の意味だろう。そして自分の中にある言葉だけが、正しいものとして考えてしまうことでトラブルが生じる。
実際SNS上のやり取りでは言葉の取り違いによるトラブルが頻繁に起っている。例えば、ある動画クリエイターが投稿した動画での発言に対し、一部の視聴者が批判のコメントを送るといったことがある。明らかに相手を傷付ける内容とは別として、捉え方の違いから批判が生じているケースは多い。批判をする人は、その言葉に他の意味や使い方があることをよく調べたりせず、自分の考えだけが正しいと思ってしまうのである。こうして同じ言葉であるのに共有することができないといった事態が生まれる。
このような状況を回避するためには、同じ言葉でも解釈を増やすことで、共有できない言葉を減らすことができると考える。そのためにインターネットを使用するのは有効的だ。昔は辞書でしか調べることができなかった言葉が今ではスマートフォンで簡単に調べることが可能だ。さらに、インターネットでの検索では、言葉の意味だけでなく、その言葉に関連した様々な情報を同時に得ることもできる。これを繰り返すことで自分の言葉の引き出しが増え、相手とのコミュニケーションが円滑に進むことに繋がるだろう。
以上のように共有できない言葉は存在する。しかし、自分が捉えている言葉の意味だけを信じるのではなく、その言葉に含まれている感情や出来事など多くの関連したものを吸収していくことで、共有できない言葉を減らすことができると考える。
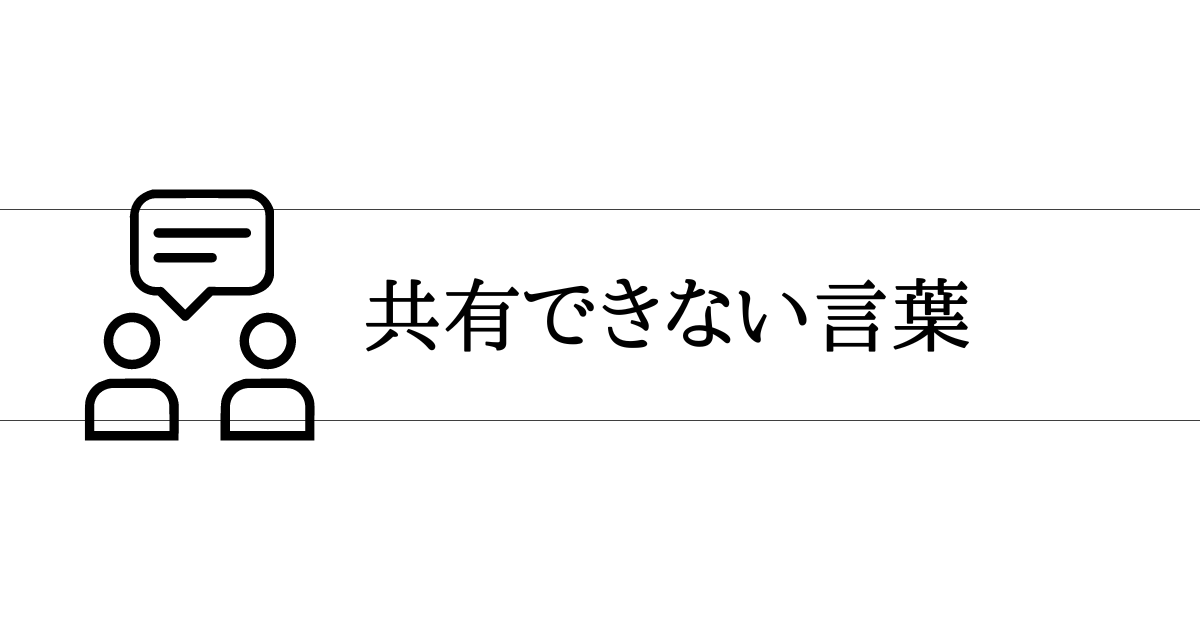
コメント