平成25年度【2013年度】慶應義塾大学法学部小論文解答例「内閣制度の問題点」です。
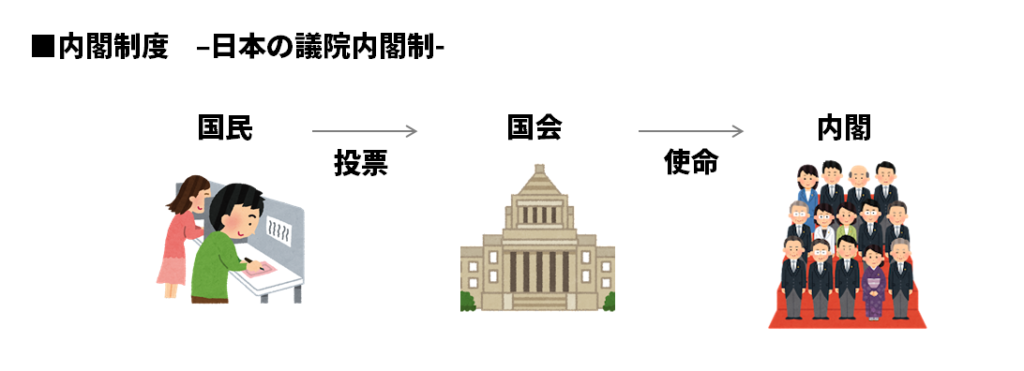
↓
具体的には、
・維新に功績のあった薩長4人ずつの計8人が政権を独占して、薩長間のバランスを取ろうとしたため、総理大臣がリーダーシップをとろうとしてもうまくいかないことが多かった。
・諸大臣は、各省の利権を代表するという側面が肥大化しはじめ、ついには各省間のむき出しの利害対立、政策的競合に直面せざるを得なかった。
・各省と関わりの大きい人物が総理大臣になったので、主導よりは調整を行う必要があった。
↓
以上の理由より、内閣制度発足時における首相のリーダーシップは主導よりも調整に重きが置かれていたと分かる。その結果、条約改正交渉のような内閣全体の意思統一が必要な場面ではその特徴が弊害となって現れた。
内閣制度の問題点(慶應法2013)解答例
内閣制度を多くの問題を抱えていた。1つ目は内閣において、薩長のバランスが意識されることで制度的枠組みに馴染まない性格を持っていたこと。2つ目は諸大臣の各省の利益を代表するという側面が肥大化してしまい各省の割拠性が現れたこと。3つ目は藩閥内の各省とも無縁ともいえない人物が政権のトップとして内閣内の各省間の利害対立や政策的競合に直面しなくてはならなくなったことだ。これらの理由から首相の強力なリーダーシップを保証する「内閣職権」は発動しないことが前提とした建前上のものとなってしまい強力なリーダーシップのもとに実行しなければならないような政策の実行に苦戦した。
私は現在の内閣総理大臣のリーダーシップの在り方は、時代に合わないため変革するべきだと考える。日本の内閣総理大臣は、与党の党首が国会議員と兼任することが慣例となっている。そのため総理大臣は、議会や与党とは相互に依存し合う関係となってしまっている。私は、この仕組みが一国の首長としてあるべき国民を第一に考え主体的に行動するリーダーシップの在り方を阻害してしまっていると考える。実際に日本の岸田総理は、総理大臣に就任後も、派閥の長に座り続け、常に他の派閥や要人の顔を伺う政治を行ってしまっていると言われている。そのため総理の権限は弱く根本的な改革を行うことは極めて難しい。それに対し、国の首長が国民による直接選挙で選ばれるアメリカなどの国では大統領は、議会から独立した強力な権限を持っており、リーダーシップが発揮しやすい環境が整っている。したがって、国民意見を反映させた政策を容易に実行しやすい。
現在日本は転換期を迎えている。超少子高齢化社会、過度に進行する物価高、経済不況、中国・ロシア・北朝鮮の脅威など多くの問題が山積みである。しかし現行の内閣総理大臣のリーダーシップでのあり方では、これらの問題の根本的な解決は難しいのではないだろうか。アメリカのように内閣総理大臣にも議会から独立した強力な権限を与え、選出の際も国民の声が反映されやすい方法を採用するなど、より国民に寄り添った形で首相のリーダーシップが発揮できるような制度の変更が、これから必要になってくるだろう。
内閣制度の問題点(添削一部抜粋)
-省略-
後半の自身の意見ですが、「出だし(最初の文)」に具体性に欠け、徐々に題意からかけ離れてしまった印象です。今回の問題は、「現代の内角総理大臣のリーダーシップのあり方」なので、今回のZさんの論評から構成案としては、
<構成案>
(主張)Aのような現代の内閣総理大臣のリーダーシップのあり方は、Bの点において時代に合わなくなったため変革すべきである。国民に寄り添い主体的に行動できるリーダーシップのあり方が求められると考える。
(背景・事実確認)~の慣例があり、~依存し合う関係になっている。これでは、Aのようなリーダーシップになる。実際、現総理大臣の岸田首相は~。Bの点において時代に合わない。
(展開)現代の日本は転換期を迎えている。<少子高齢化など具体例>
(具体策)国民に寄り添い主体的に行動できるリーダーシップを発揮できる制度づくりとして、アメリカなどで首長を選ぶ際に行われる直接選挙も一つの選択肢であろう。これにより、~となる。
(まとめ)以上のように、リーダーシップのあり方として、~だ。そのためには、国民の声が反映されていることが前提にある。
-省略-
「私は現在の内閣総理大臣のリーダーシップの在り方は、時代に合わないため変革するべきだと考える。」の部分は、
もう少し具体的に!
(修正案)~のような現代の内閣総理大臣のリーダーシップのあり方は、~点において時代に合わなくなったため変革すべきである。
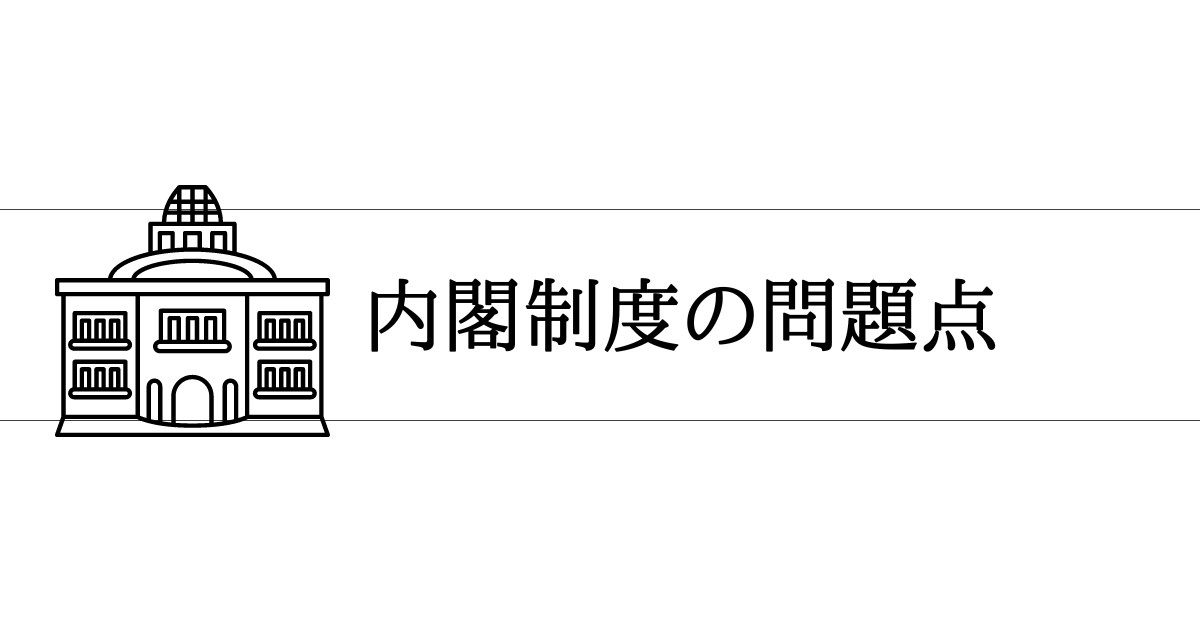
コメント