平成15年度【2003年度】慶應義塾大学法学部小論文解答例「臓器移植」です。
【問題】著者の議論を踏まえて「公共化される身体」という考え方に関するあなたの意見を述べ、それと関連づけて、公共性の問題一般について、自由に論じなさい。
臓器移植(慶應法2003)
臓器移植という個人を越える間身体的な医療行為では、臓器提供者と手術受ける人の相互の不可分性と自律性は解体されて組み替えられ、その組み換えは。第三者としての医療機関の介入によって支えられることになる。このような医療化された社会では、個人の境界が薄れてゆき死が見えなくなっていき、殺すと壊すの違いも感知しにくくなった。フーコーが言うように権力は、人間を個別化する形で行使される死を与えることで、機能する権力からひとまとまりの置き換え可能な集合的人間を対象に行使される死を放置する。生を管理する権力へと性格を変えた。そして様々な局面から分析しそこに、「バイオポリティクス」の誕生をみた。そこでは死による個別化は重要でなく、死は権力の管理から次第に排除される。生命には機能はあっても象徴的意味はないとされる。現在の状況は、その延長線上にあり、身体は、「わたし」から離れ無名の公共性に委ねられようとしている。以上が筆者の主張である。
私は身体の公共化は避けることができないのではないかと考える。確かに個人の意見を尊重することは、重要である。しかし、臓器移植などの身体の問題に関して言えば、公共化を行わなければ、かえって臓器の商業化が進んでしまうのでないだろうか。現在、公共機関が臓器の利用と分配を決めている。それが、個人の意思に完全に委ねてられてしまうと臓器提供を受けることは、特権的な人や金持ちの人しかできないということになってしまい不平等な状況が作られるてしまうだろう。したがって、医療技術が発達した現在、身体に委ねる関わる問題が公共性にある程度、委ねられることはやむを得ない。
それでは、この問題も含めた社会の諸問題に対して、公共性はどのように関わっていけばよいのだろうか。社会の利益と意思である公共性はしばしば個人と対立する。具体的な例が、沖縄の米軍基地問題である。米軍の存在のおかげで日本は、平和が保たれている一方で、現地の人々は航空機の事故や騒音などに苦しんでいる人も多い。このような場合、公共性やその側に立っている人間は、その実現を第一にして、多少の犠牲は目を逸らしてしまっていることが多い。いつまでもこの対立は終わらないだろう。そうではなく公共性を実現するにあたって、副次的に起こる悪影響をなくすことはできずとも最小限に抑え、個人に対して歩み寄ろうとする姿勢が必要だろう。
公共性の問題についての新たな視点(発想、着眼点)
・「公共の福祉」を前提とした「当事者意識」という視点。Aさんが今回例示した米軍基地問題の件もそうですね。自分の立場とは、反対の立場にある人になってみる、想像してみる「当事者意識」が大事ですね、今回の記述にも、「公共の福祉」「当事者意識」といった文言があるとよかったと思います。
「公共の福祉」「当事者意識」という視点を挙げたのも、慶應法は、繰り返しなりますが、どこまで「基本的人権」の範囲が及ぶのかという受験生の見解を示させる課題が多いような気がします。
※「公共の福祉」…ざっくりいえば、社会全体の共通の利益。ほかの人の人権との衝突を調整するための原理。
日本国憲法第12条
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
・国民の臓器提供の意思表示が低い段階(臓器提供意思表示カード自体の存在または存在医を知らない人も多い状況)で、公共性は担保されるのかという視点。つまり、イニシアチブ(主導権)を特定の人達・機関に委ねてしまうことになりかねないという問題意識。「公共の福祉」の濫用につながりかねない。
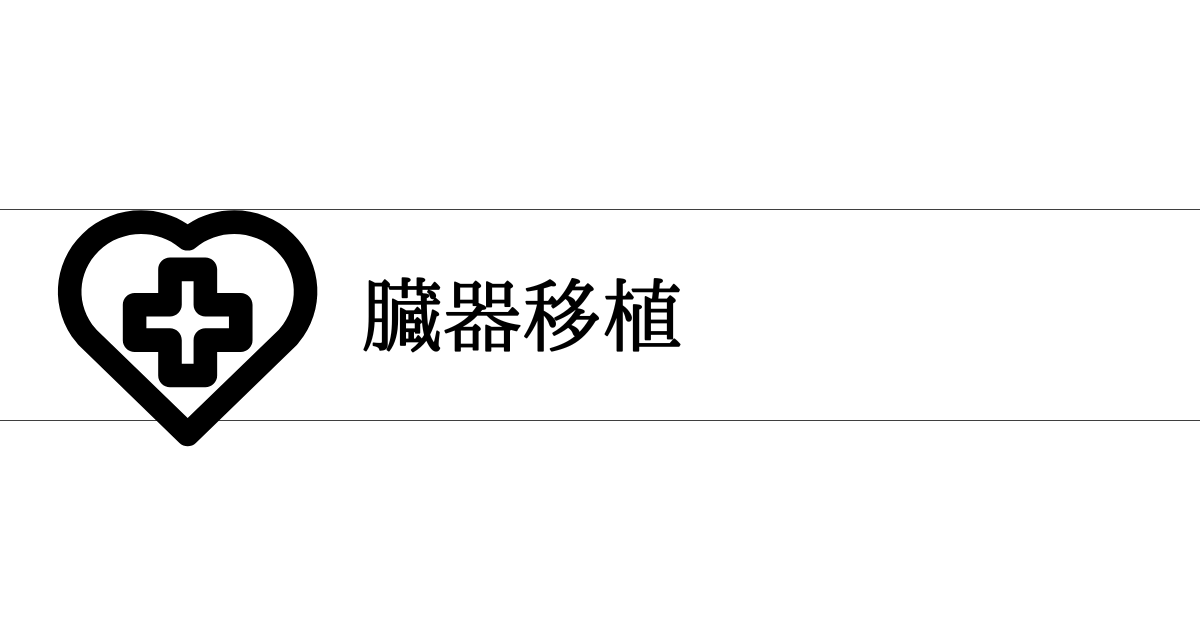
コメント